前回紹介した
子授指南書
『黄素妙論(こうそみょうろん)』
著:曲直瀬道三
手書きの原本は、1552年に
戦国武将の松永久秀に書き送ったもの
(版本:1620年・1808年刊行)
【画像】1808年(文化5年)刊行版
京都大学附属図書館所蔵『富士川文庫』より
いつの時代も
子を求める夫婦がいる。
それは
血を継なぎ、家を存続させ
次の世代が継承するため。
子孫を残すことは
ただ単純に、本能でもある。
しかし
子をなかなか
授かることができず
悩む夫婦が
過去にも数多くいた。
公家や武家、商家や農民
ひいては天皇家においても
不孕は、大きな問題だった。
※不孕(ふよう):不妊のこと
東洋医学は
1500年の歴史がある。
日本最古の医学書に
『医心方』が現存する。
平安時代(984年)に
宮中医官を務めた
鍼医の丹波康頼(たんば やすより)が
朝廷に献上した全30巻の医学書。
その中に
巻二十八 『房内篇』が存在する。
2020年の
現在から見ると
1036年前の
医学書に「求子」の記載がある。
すでに、受胎理論と治療法が
克明に記されているから驚きである。
いつの時代も
子を求める夫婦がいる。
●奈良時代
●平安時代
●鎌倉時代
●室町時代
●安土桃山時代
●江戸時代
1500年間
各時代において優秀な医師
東洋医(鍼医・漢方医)が存在していた。
時代に合わせ
不孕に悩む夫婦たちに
子授の治療をして
子を成さしめている。
得られた成果を
子授指南書に書き残し
時代を経るごとに
洗練され治療効果を高めて来た
子授指南書の恩恵を受け
子を授かった夫婦は数知れぬ。
明治・大正・昭和・平成
そして令和の時代にも
ありがたいことに
子授指南書の
恩恵を受けることができる。
東洋医学には
歴史ある不妊治療が存在する。
その存在を
知る者と知らぬ者にわかれる
それも運命であろう。
____________________
〔 東洋医学の不妊治療を啓蒙のため 〕
◎ ランキングに参加中 ◎
おかげさまで
健康と医療(不妊)部門:2位
不妊(赤ちゃん待ち初心者):1位
不妊(高齢赤ちゃん待ち):5位
赤ちゃん待ちブログ総合:16位
=応援クリックおねがいします=
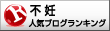 |
____________________

